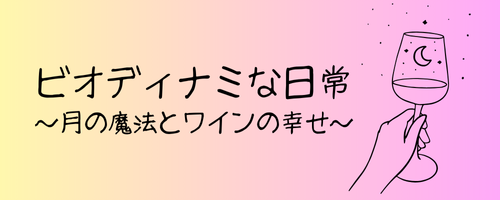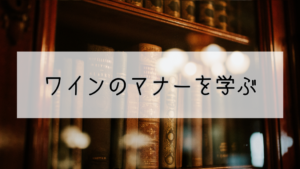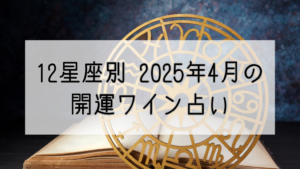ビオディナミワインとは?
皆さま、こんばんは。「ビオディナミな日常」の管理人、Kurinoです。
3回目のレッスンは本サイトの本丸、ビオディナミワインについて触れていこうと思います。ワインに興味を持ち始めると自然派ワインやビオディナミワインという言葉に触れる機会が増えると思います。これらは農薬や化学肥料を極力使わない~全く使わないことをポリシーとしています。ビオディナミワインはそこからさらに、天体のリズムを重視して造る特別なワインなのです。

ビオディナミワインとは?
ビオディナミ(Biodynamie)とは、オーストリアの哲学者ルドルフ・シュタイナーが提唱した農法で、自然界のエネルギーや天体の動き、つまり月の満ち欠けや星の動きに合わせて農作業を行うのが特徴です。ブドウの種まきや収穫、瓶詰めのタイミングなど、月や惑星の位置を記載したカレンダーに従って作業を行います。使用して良い肥料(ビオディナミではこれらをプレパラシオンと言います)についても決まりがあり、牛の角や水晶の破片、タンポポの花などを畑に埋めることもあるそうです。1924年頃にフランスを中心に広まり始め、今では世界中に広がっています。1985年にはビオディナミ認証機関(デメター / Demeter)が設立され、基準を満たしたものだけ認証が与えられます。このサイトでもデメター認証のワインを多く紹介していきますので、楽しみにしていてくださいね。
他のワインとは何が違う?
「ビオディナミ」とよく似た言葉に「ビオロジック」という農法があります。これは化学的に合成された農薬や肥料を一切使わない農法でビオディナミとよく似ていますが、ビオディナミはビオロジックに加えて月や星の動きを意識した農作業と、呪術的ともいえる肥料(プレパラシオン)を用いることが大きな違い。科学的な根拠は残念ながら現時点ではないのですが、日本ソムリエ協会でもビオディナミワインの品質の良さを認めています。ワイン造りで覚えておきたい農法は他にも減農薬の「リュット・レゾネ」などがあります。ブドウは病気になりやすく、果実なので虫が多く寄ってくるため、農薬をたくさん使うのがこれまでの主流でした。しかし、環境意識が高まる昨今、「それってどうなのだろう」と思い始めた生産者が増えつつあります。栽培技術が高まってきた背景もあるので、今後は少なくとも農薬の使用は減ってくると思います。
ビオディナミワインの味わいと特徴
農薬、肥料など、化学的な介入が少ないため、土地の個性がより強く表現される傾向にあります。あくまで私の個人的な感想ですが、果実味が豊かでミネラル感があるもの、独特の旨味があるもの、繊細だけど余韻が長く続くもの、など一口にビオディナミといっても、とてもバリエーションが豊富です。ラベルのデザインも拘ったものが多く、1冊の本を選ぶような感覚でワイン選びが楽しめます。ただ、昔ほどではないのですが、いやな匂いのするものに当たる確率が少しだけ高め。出荷後の保存状態が悪かった、というよりは作り手の技術力や目指す方向性の表れなのかな、という気がしています。
ビオディナミワインの有名な生産者
高級ワインで有名なロマネ・コンティ。いつか飲んでみたい1本なのですが、実はこのロマネ・コンティもビオディナミ農法でブドウを栽培していることをご存じでしたでしょうか?私は最近まで知らず、意外と大手もこの農法を取り入れているのだな、と感心しました。他に有名な生産者の名を上げると、フランス・ロワール地方のニコラ・ジョリー、ブルゴーニュ地方のドメーヌ・ルロワ、ジャン・クロード・ラトー、アルザス地方のピエール・フリック、ローヌ地方のミシェル・シャプティエなど。フランス発祥なだけあって、フランスに有名生産者が多く集まっていますが、今は世界中で取り組まれているので今後が楽しみです。